| (1) |
「身を粉(こ)にする」の意味と語源:「自己を犠牲にして献身的に勤めること」 |
|
|
<語源>
江頭五詠 「丁香」
『丁香體柔弱 亂結枝猶墊。
細葉帶浮毛 疎花披素艶。
深栽小齋後 庶使幽人占。
晩堕蘭麝中 休懷粉身念。』
(「杜甫全詩集,第2巻」) |
|
 <丁子> <丁子> |
|
↓ |
|
|
(読み下し)
丁
香 , 體
柔
弱
なり。
亂
結
,
枝
猶
墊
る。
細
葉
,
浮
毛
を
帶
ぶ。
疎
花
,
素
艶
披 く。
深
く
栽
す
小
齋
の
後
,
庶
わくは
幽
人
をして
占
めしめん。
晩 に 蘭
麝
の
中
に
堕
つるも,
粉
身
の
念
を
懷
くを
休
めよ。
(詩意)
(植物としての)丁子は,その幹は柔かく弱そうに見えるが,それでも枝は茂り,垂れ下がっている。
その細い葉の表面には産毛がたくさんあり,花はまばらではあるが,つやつやしている。
この木を小さな書斎の後ろに植えて,占有したいものである。
晩年に,蘭麝の香のする貴いものの中に落ち込んだとしても(宮廷に勤めるような機会が訪れたとしても),おのが身を粉(こ)にしてまで(自己を犠牲にしても誰かのために尽くそうなど)と,考えるのは止めたいものだ。
(そんなことをすれば、きっと自らが傷つくことになるのだから・・・) |
(注)
(a)江頭五詠:中国の代表的詩人である杜甫が,揚子江のほとりの粗末な建物で詠んだとされる五つの歌。
(b)丁香:丁子(ちょうじ)のこと。丁子は植物であり,お香の原料にもなります。
中国語で「丁子」は「釘」を意味しますが,これは,ツボミの形が釘の形に似ている(上の写真参照)
ことからついたようです。
(c)體:=体(たい)。
(d)小齋:小さい書斎。
(e)幽人:自己。
(f)蘭麝:高貴に匂うもので,「宮廷」を意味します。
⇒<参考>正倉院に,有名な香木である蘭麝(奢)待があります。
|
|
『天下一の名香あせず-1200年前の正倉院・蘭奢待- 』
『表面樹脂が封じ込める 阪大研究 』 (読売新聞 2003,6,17<夕刊>より引用), |
|
|
|
|
|
『「天下第一の名香」として奈良・正倉院に伝わり,足利義政や織田信長(後に明治天皇)が楽しんだとされる香木「蘭奢待」が現在も中国から渡来したとされる約1,200年前当時の芳香を保ち続けていることが大阪大総合学術博物館の米田該典助教授(薬資源学)による成分分析でわかった。』 |
|
|
|
 |
←「蘭奢待」
<長さ1.56m,重さ11.6kg> |
|
|
|
『蘭奢待はインドシナ半島産の可能性が高い沈香という種類の香木で,火であぶると甘い芳香を放つ。長さ1.56m,重さ11.6kg。天皇もしくは天皇の許可を得たものだけが切り取ることができ,信長らが切り取ったとされる付箋が残っている。
香りは有機化合物「セスキテルペン」が組合わさった様々な成分からなり,米田助教授は蘭奢待から採取した微量の成分をクロマトグラフィー法で分析し,現代の沈香と比較。その結果,どの成分構成もほぼ同じで,香りが損なわれていないことがわかった。
聖武天皇の遺物として正倉院に残る沈香「全浅香(ぜんせんこう)」も香りの成分に変化のないことが判明。これに対し,同じ宝物の白檀(びゃくだん)の破片は香りが逃げてしまい,普通の人間の嗅覚ではにおいがわからないほど成分が変化していた。
|
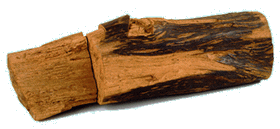 |
|
←「全浅香」
<長さ1.06m,重さ16.7kg>,
|
|
米田助教授は「沈香は時間が経つにつれて表面の樹脂が固まり,香りを封じ込めているのではないか」と話している。』 |
|
|
|
|
|
(g)粉身念:粉身とは香の縁語で,丁子をお香の原料にするのに粉砕することから,身を粉に砕くこと=
「自己を犠牲にして献身的に勤めること」を意味します。
|
|
|
| (2) |
「粉骨砕身」の意味と語源:力を尽くして努力すること。 |
|
(a)「禅林類算(ぜんりんるいさん)」 : 『粉骨砕身するも,此の徳に報い難し』
⇒(力の限り尽くしても,仏の恩に報いるのは難しい。) |
|
|
|
(b)「証道歌(しょうどうか)」:
(唐の僧玄覚(げんかく)の禅の教えを説く歌): 『粉骨砕身未だ酬(むく)ゆるに足らず』
|
|
|
| (3) |
「玉石混交」の意味と語源:「玉」(ぎょく)は宝石の意味があります。宝石と石が混ざっているように,
良いものと悪いものが入り交じった状態をいいます。 |
|
晋の渇供(かっこう)「抱朴子」外扁の尚博扁で,軽薄な詩をもてはやす世間を嘆いた言葉が
語源とされています。
|
|
|
| (4) |
「和光同塵」の意味と語源:優れた能力を隠して,俗世間の人々と交わること。
「和光」は本来の光(知恵)を和らげ,隠すこと。また,「同塵」は世の中の塵と同じになること。
「其(そ)の光を和げ,其の塵に同じうす」と、そのままの文章があります。(出展:「老子」)
“人はとかく自分の才能や知識をひけらかし目立とうとする。すると,何か禍いが起こった時に,
目立つ者がまっ先に害にあう。だから,なるべく才知は表に出さず,俗世間の塵の中にまみれて
いるのが良い”という人生哲学です。 |
|
|
| (5) |
「粒々辛苦」の意味と語源:こつこつと地道に努力して,物事を成し遂げること。
「粒々皆辛苦」の略で,米一粒一粒が,農民の努力や苦労の賜であることから。
唐の李紳(りしん)の詩の句に基づきます。
--農を憐れむ 李紳--
『禾(いね)を鋤(す)いて日午(ひご)に当る
汗は滴る禾下(かか)の土
誰か知らん 盤中(ばんちゅう)の食(そん)
粒粒皆辛苦なるを』
⇒(稲の草取りをして、午時(ひるどき)になると、汗が土に滴り落ちる。
皿に盛られた食べ物は,一粒一粒がみな農民の苦労のお蔭だと誰が知る。)
|
| (6) |
「一粒万倍(いちりゅうまんばい)」の意味と語源:一粒の籾(モミ)が万倍となって,稲穂のように実るということ。
わずかなものが非常に大きく成長することの例えとされます。
また,少しでも粗末にできないという気持ちも表します。
「一粒万倍日」:大安と並んで縁起が良く,何事を始めるのも良いとされる吉日のことです。
|
例えば 2014年の一粒万倍日 |
|
|
|
| 1月 |
4,5,8,17,20,27 |
5月 |
8,9,20,21 |
9月 |
2,10,17,22,29 |
| 2月 |
1,4,11,16,23,28 |
6月 |
1,2,15,16,20,21 |
10月 |
4,14,17,26,29 |
| 3月 |
5,15,20,27 |
7月 |
10,13,22,25 |
11月 |
10,11,22,23 |
| 4月 |
1,11,14,23,26 |
8月 |
3,6,9,16,21,28 |
12月 |
4,5,7,18,19,30,31 |
|
|
|
|
| |
|
 |
鼻煙壷(びえんこ): |
大阪市立東洋陶磁美術館において,平成20年7月19日から9月28日まで,鼻煙壷1000展が開催されました。日本人コレクター(沖 正一郎氏)が大阪市に約1,200点もの寄贈をされたことを記念してのものでした。
鼻煙壷(びえんこ)とは,粉末状の嗅ぎタバコを入れる小さい(高さ5~6cm)容器のことで,表面に微細できれいな文様が施されたものです。
これらは中国の清朝の宮廷で流行したものが多く,容器の材料は一般的な陶磁器からガラス(赤,白,緑,透明),金属,石(ごく普通のものからトルコ石,孔雀石,石英・・・),さらには動植物(象牙や種etc)にいたる多くのもので,(形も凝ったものが多い),興味深いものでした。
|
|
|
|
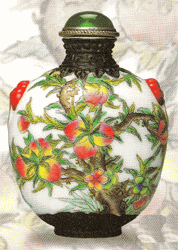 |
|
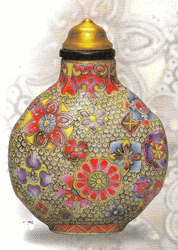 |
|
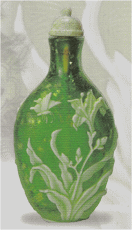 |
|
 |
|
|
|
|
(1)
粉彩桃樹図鼻煙壷
(パンフレットから引用) |
(2)
夾彩花文鼻煙壷
(パンフレットから引用) |
(3)
緑ガラス白被せ
花文鼻煙壷
(パンフレットから引用) |
|
その他の粉彩文様鼻煙壷 |
|
|
(1)と(2)は陶磁器製容器の上に,(3)はガラス製容器の上に彩色したものです。
以下は場内での説明文です。
|
(1) |
粉彩桃樹図鼻煙壷 |
|
|
|
|
|
『器表の一部に花樹を描き,その先端が裏面に延長していく表現方法は,清時代特有のものです。本作品もその手法で桃樹が描かれています。桃は長寿を表し,蝙蝠(こうもり)は音が福に通じ,全体で寿福を表しています。』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
夾彩花文鼻煙壷 |
|
|
|
|
|
『器表全面に様々な花文をちりばめ,余白を魚々子(ななこ)地で埋めた装飾的な作品です。花文には,粉彩磁に特有の中間色が多用され,花弁の内側は丁寧にグラデーションで塗り分けられています。』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ちなみに「粉彩」とは,ヨーロッパの七宝技術の影響を受けて清朝時代(1,700年代)に完成した上絵の一種で,白磁の容器表面に不透明な白色顔料で文様の下地を作り,その上から様々な色の顔料で絵付けをしたものだそうです。 i色の微妙な濃淡の描き分けが可能で,色調の変化を利用した多彩な文様表現に特徴があります。また,「夾彩」とは,「粉彩」の技法で容器の全面を埋め尽くしたものをいうようです。 |
|
|
|
|
|
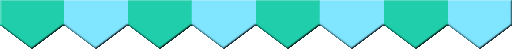
 粉粒体(ふんりゅうたい)とは :
粉粒体(ふんりゅうたい)とは :
 各種粉粒体(粒子)の粒度範囲(サイズスペクトラム)
各種粉粒体(粒子)の粒度範囲(サイズスペクトラム) トップページへ戻る 前の部屋へ ,次のページへ
トップページへ戻る 前の部屋へ ,次のページへ 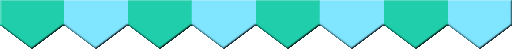
 粉粒体(ふんりゅうたい)とは :
粉粒体(ふんりゅうたい)とは :
 各種粉粒体(粒子)の粒度範囲(サイズスペクトラム)
各種粉粒体(粒子)の粒度範囲(サイズスペクトラム) トップページへ戻る 前の部屋へ ,次のページへ
トップページへ戻る 前の部屋へ ,次のページへ