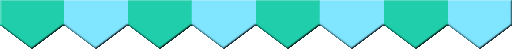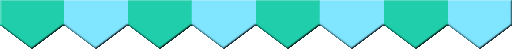|
 |
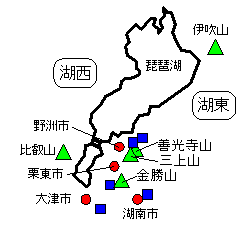 |
磨崖仏とは,自然石の崖などに彫刻された仏のことです。
そんな磨崖仏が,滋賀県南部(湖南)にはいくつか見られます。
磨崖仏は奈良時代後期〜鎌倉・室町〜江戸時代初期頃に作られていますが,なぜ近江南部にたくさん見られるのか?また,険しい山岳地帯に多く見られるのか?
これら磨崖仏や石塔などの石の文化は,遠い昔,大陸(中国や韓国)からの渡来人が伝えたものと思われます。磨崖仏が近江に多いのは,近江に根付いた,この渡来人に由来する石の文化と「修験道」とが結び付いた結果であるようです。
(修験道とは,仏教の一派である密教(天台宗・真言宗)で行われていた山中での修行と日本古来の山岳信仰とが結びついたものです。その主な舞台は奈良・三重〜京都・滋賀の山岳地帯でした。)
|
|
|
|
|
|
 |
湖南市の磨崖仏(平成24年1月22日) |
| (車谷不動磨崖仏) |
|
 |
湖南市岩根車谷にある磨崖仏です。
この像は高さ6.2m,幅2.0mの自然石(花崗岩)に彫られており,
通称 車谷不動といわれています。
像高さは4.3m,肘幅2.1m,顔幅0.8mとかなり大きく,また,
右手に持っている宝刀の長さは2.3mもあります。
江戸時代作とのことです。
湖南市には,この他にもいくつかの磨崖仏があるようです。
(a)菩提寺の閻魔像(国指定文化財)
(b)岩根・不動寺の磨崖不動明王像(市指定文化財)
(c)妙感寺裏山の磨崖地蔵菩薩像
←(見上げているのは私です(^^)) |
| |
|
|
|
|
白洲正子さんの著書「近江山河抄」には以下の記述があります。
『水口の西北,東海道にそって,あまり高くない山が続いており,この丘陵を「岩根」とよぶ。高くはないが奥深い森林地帯で,
すぐそばを東海道が走っているのが別の世界のように見える。
その名のとおり,岩石の多いところで,山中には善水寺という寺があり,石仏がたくさんかくされている。・・・(中略)・・・
近江には奈良や京都に匹敵する美術品が無いと書いたが,石造美術だけは別である。美しい石材に恵まれていたのと,
帰化人の技術が手伝ったのに違いない。』 |
|
|
|
 |
野洲市の磨崖仏
|
(1)妙光寺山磨崖仏(平成26年5月11日)
京都技術士会のメンバーと,三上山〜妙光寺山 登山兼ハイキングに行きました。
磨崖仏は妙光寺山からの下山道で観察できました。
(a)三上山(別名:近江富士,432m)は,御上神社の御神体となっています。
御上神社の社記によると,天之御影神(あめのみかげのかみ)(=天照大御神の孫)が,孝霊天皇6年(296年)6月18日に
三上山に降臨したとのこと。そこで神主の御上祝(みかみのはふり)が,三上山を清浄な地とし神体山としてあがめ奉った,
とされています。
御上神社の秋の例祭はずいき祭りとして知られていて,天之御影神は鍛冶の神様ですが,この近くで多くの銅鐸や
国内最大の銅鐸が見つかっているのも無関係ではなさそうです。
 |
|
 |
|
 |
|
| 三上山全景 |
|
御上神社の前で |
|
登山道の中間にあった[割れ岩]
(人が1人やっと通れる幅) |
|
| |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 三上山 山頂 |
|
三上山をバックに(妙光寺山への途中) |
|
(b)妙光寺山(270m)へは,三上山から尾根伝いに行けました。
 |
妙光寺山の山麓にある磨崖仏です。
崖に露出する岩に畳1枚ほどの切り込みを作り,その中に,
高さ1.6m,厚さ10cmの地蔵立像が彫刻されています。
宝珠・錫杖(しゃくじょう)を持ち,線刻の蓮華座の上に沓(くつ)を
はき,立っているのが珍しいようです。
元享4年(1324年)7月10日(鎌倉時代)の作です。 |
|
|
| |
(2)福林寺跡磨崖仏(平成26年11月4日)
野洲市の山中に福林寺跡磨崖仏があるというので,仕事帰りに寄ってみました。
野洲中学横に車を止めて,徒歩10分ほど。磨崖仏入口と書かれた看板の先は細い道になっており,その周りは
うっそうとした木々に覆われ,それらしきものは見あたりません。
この近くには,5月に登った三上山の帰り道で見た妙光寺山磨崖仏がありますが,白州正子さんが著書
「かくれ里」の中で,『ある日,私は前野さんの案内で石仏を見に三上山から鏡山のあたりを歩いたが,
肝心の石仏は見つからず山の中で迷ってしまった。』というのもうなづけます。
そんな中,やや大きめの石(直径3〜4m位)の横に,観音像1体と如来像2体が彫られた磨崖仏(石仏)がありました。
それらは高さ50cmほどの比較的小さい石像ですが細部まで彫刻されており,その近くにはやや小さめの石仏も
多数点在していました。室町時代作とのことです。福林寺跡という石碑もありました。
|
|
|
 |
栗東市の磨崖仏
平成26年10月26日,金勝山(こんぜやま)ハイキングに行ってきました。
金勝山は,滋賀県の湖南地方にある山々の総称です。竜王山(605m)が最高峰です。
主なコースは以下のとおりです。
桐生キャンプ場⇒オランダ堰堤⇒逆さ観音⇒狛坂磨崖仏⇒竜王山(馬頭観音堂)⇒金勝寺(こんしょうじ)⇒
「こんぜの里」
 |
|
 |
|
 |
|
| (a)オランダ堰堤 |
|
(b)さかさ観音 |
|
(c)狛坂磨崖仏 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| (d)金勝寺 |
|
(e)金勝寺 ぐんだり明王 |
|
(f)金勝寺 女神座像
<文献3)より引用> |
|
(a)オランダ堰堤は,明治時代にオランダ人デレーケの指導のもとで築造された切石積みアーチ式堰堤です。
そもそもこの地域では,奈良時代頃から継続的に奈良の宮殿や社寺の建設資材として木が伐採され,
江戸時代にはほぼ禿げ山状態になり,河川の氾濫や土砂の流出などの災害が多発していました。
その対策として堰堤が築かれました。
(b)さかさ観音はオランダ堰堤の上流にあり,金勝寺への参道の途中にありました。
鎌倉時代作で阿弥陀三尊石仏が彫刻されていますが,堰堤築造寺に山上からずり落ちてさかさに
なってしまったようです。
(c)狛坂磨崖仏(狛坂寺跡磨崖仏):急な坂道の途中に有り,高さ6m・幅5mの1枚岩(花崗岩)に,高さ3mの仏が
彫られています。ここには,かって狛坂寺というお寺もあったことが判明しており,そのお堂の中に入っていた
可能性もあるようです。奈良時代後期作で,製作は渡来系工人によると考えられています。
白州正子さんは,著書「かくれ里」で以下のように記述しています。
『磨崖仏は聞きしに優る傑作であった。見上げるほど大きく,美しい味の花崗岩に三尊仏が彫ってあり,
小さな仏像の群れがそれを取り巻いている。奈良時代か平安初期か知らないが,こんなに迫力のある石仏は
見たことがない。人里離れたしじまの中に,山全体を台座とし,その上にどっしり居座った感じである。』
| |
|
<再生ボタンを押してください> <音声あり> |
|
| |
|
|
NHK-BSプレミアム
2006,01,02
『白洲正子が愛した日本』から引用
|
(d,e)金勝寺:奈良平城京の東北鬼門を守るお寺として建てられたが火災で焼失。江戸時代に再建許可を得たが,
現在もその時の仮の堂のままだそうです(普段は無住)。
「ぐんだり明王」は高さ4mあり,檜の一材から掘り出されています。
(f)金勝寺の女神座像:文献3)によれば,金勝寺には平安・鎌倉時代作の神像が10数体伝わっています。
女神座像はそのうちの1体で,檜材で高さ29cm,すばらしいできです。
白洲正子さんは,著書「近江山河抄」では以下のように記述しています。
『阿星山は金勝山の峰続きにある。というより,金勝山の一部とみなした方がいい。地形がそうであるように,かっては金勝を
めぐる一大宗教圏に属していた。そういっても大げさではないほど,この辺りにはお寺が密集しており,草創当時の壮観が
偲ばれる。狛坂廃寺の石仏については前にも書いたことがあるが,一口に金勝山といっても,その周辺を歩いてみると,
想像以上に規模の大きいことに驚く。信楽の宮の背後には,莫大な勢力と財産が蓄積されていた。奈良の大仏は忽然と出現
したのではない。三千世界を象徴する毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)の理想は,金勝山を中心とする信仰と歴史の層の厚みによって,
はじめて達成することを得たのである。』
|
|
|
 |
大津市の磨崖仏(富川磨崖仏)
平成26年11月30日,大津市南部(大石東の近く)の信楽川沿いの山中に,磨崖仏が有るというので見てきました。
422号線沿いに看板を見つけましたが,周りは山岳地帯で寺らしきものは無く,木々で覆われた急な道を昇っていくと,
急にその磨崖仏が現れました。
高さ約30m・幅約20mを越す直立した大岩(花崗岩)に,高さ4mほどの磨崖仏(阿弥陀仏)が彫刻されていました。
看板によると,ここは岩屋不動院明王寺の跡で,寺は奈良時代(霊亀元年(715))に開かれたと伝えられ,
当初の本尊は石造の釈迦如来像であったとのこと。
左右にも菩薩立像と不動明王立像が刻んであり,これらの彫刻は,鎌倉時代作のようです。
耳の当たりに雨水の垂れた跡があることから,俗に「耳だれ不動」と呼ばれていて,耳の病に御利益があると
されています。
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| 磨崖仏へ続く参道 |
|
像の高さは約4mあります |
|
左下の菩薩立像 |
|
|
|
白洲正子さんの記述は以下のようになっています(「かくれ里」)。
『その大石から,信楽川にそって,ニキロほど南に行ったところに,富川の石仏がある。・・・(中略)・・・。
鎌倉時代の雄大な阿弥陀三尊で,一名「耳垂れ仏」ともいい,耳の病に効くという民間信仰があるが,お呪いのために,
石を切っていく風習があるのは困ったことである。
古くはここに富川寺が建ち,興福寺の修業場があったと聞くが,もっと古くはやはり巨石の信仰で,古代の岩境に
仏の像が刻まれたのであろう。石を切るのは悪い習慣だが,そういう所にも生きた信仰が見られ,自然の石が仏の姿を
かりて,民間に浸透していった長い歴史がうかがわれる。』 |
|
|
 |
その他の磨崖仏
以上の他にもいくつか磨崖仏があります。
(a)多羅尾磨崖仏:甲賀市信楽町
(b)仙禅寺磨崖仏: 〃
(c)藤尾の磨崖仏(寂光寺磨崖仏):大津市藤尾;磨崖仏が寺の中に納められています。
|
|
|
|
|
|
|
<参考文献> |
|
|
|
1 |
「かくれ里」:白洲正子著,新潮社発行,1971.12 |
|
|
|
2 |
「近江山河抄」:白洲正子著,駸々堂出版発行,1974.2 |
| |
|
|
3 |
「日本の神々」:白洲正子・堀越光信・野本寛一・岡田荘司著,新潮社発行,1998.1.25 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|