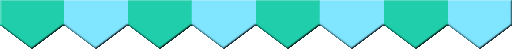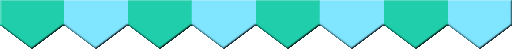宇宙の粉粒体(2)
惑星,火星
|
 |
宇宙の「塵」という言い方があり,また地球や火星などの惑星も広い宇宙では,“粒”のようなものです。
ということで,このHPでは,これらも独断と偏見で,“粉粒体”の範疇に入れることにしました。
ここでは,変わった粉粒体の例として,「惑星」と「火星」について,紹介しています。 |
|
 |
惑星
|
: |
広い宇宙では,地球や火星などの惑星は,“粒”のようなものです。
しかも,これら惑星は限りなく真球に近いことが知られており,真球率は,金星=1.0,地球=0.9964,火星=0.9936,木星=0.940などとなっています。
|
(1)火星
|
火星の大きさは,直径6,794km(地球の約半分)で,地球より小さいため,重力も小さく,地球の約40%です。また,自転の時間は24時間37分で地球とほぼ同じですが,公転時間は687日で地球の約2倍です(楕円軌道)。このため,2年毎に最接近日がありますが,距離が少しずつかわってきます(下図参照)。
|
| (a) |
<地球と火星の接近>(平成13年から平成22年までの2年毎の最接近日と距離)
|
| (b) |
<火星での生命存在の可能性>
------------------------------------------------------ |
|
|
|
| NASAの火星探査機(「Spirit」(1号機),「Opportunity」(2号機)が,平成16年1月4日;25日と相次いで火星着陸に成功し,探査を続けています。これら探査の最大の目的は,火星における生命存在の可能性を探ること,そのための水の存在を探ることです。 |
|
|
|
|
|
|
|
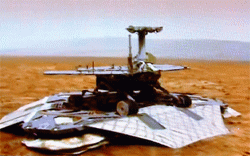 |
|
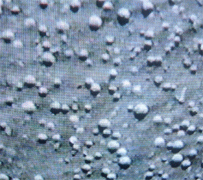 |
|
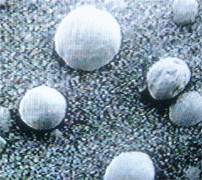 |
|
| 火星探査機Opportunity |
|
2号機が写した丸い粒子状物質(左)と拡大写真(右)
(かってここに水が流れていた可能性があります。)
NHK-TV/NASA提供(2006,5,5) |
|
|
|
|
|
|
|
| (c) |
『米探査機,火星着陸』 (京都新聞 2008,5,26より引用)
------------------------------------------------------ |
|
|
 |
|
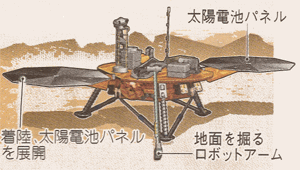 |
| フェニックスの形状 |
|
|
着陸した「フェニックス」が撮影した火星の画像。衝突を避けるため,岩石の少ない地域に着陸した。 |
|
(画像はNASA提供)
|
|
| 『米航空宇宙局(NASA)は米西部時間25日午後(日本時間26日午前),無人探査機「フェニックス」が火星に着陸したのを確認した。着陸は,2004年1月の探査車「オポチュニティー」以来,4年4ヶ月ぶり。場所は,氷の形で水が大量に含まれると考えられている火星の北極付近で,地球ではアラスカ北部に相当する。3カ月にわたって地面を掘るなどして,生命存在の条件である水の初検出をねらう。』 |
|
|
|
| (d) |
『火星の氷?探査機発見』 (読売新聞 2008,6,2より引用)
------------------------------------------------------ |
|
|
 |
| (画像はNASA提供) |
|
|
『米航空宇宙局(NASA)は1日,火星に着陸した探査機フェニックスが氷のようなものを撮影したと発表した。探査機のロボットアームに取り付けられたカメラで撮影した画像で,探査機の下の地面に,周囲よりひときわ明るく平らで滑らかな場所が写っている。
NASAは「探査機着陸する際の逆噴射で表面の土が吹き飛ばされ,下に隠れていた氷の層が露出した可能性が高い」と見ている。』
|
|
|
|
|
|
| (e) |
『氷に間違いない
−火星の写真 NASA分析−』 (読売新聞 2008,6,21(夕刊)より引用)
-------------------------------------------------------------- |
|
|
『米航空宇宙局(NASA)とアリゾナ大は20日,火星探査機フェニックスが,氷にほぼ間違いない物体を撮影したと発表した。数個の白い塊が約4日後に消失したのを写真で確認。研究チームは氷が日光を浴びて蒸発したと判断した。
|
|
 |
| (画像はNASA提供) |
|
白い塊はサイコロ大で,15日にロボットアームで地面を掘った時,深さ5cmの溝の底に露出。同大のP・スミス博士は記者会見で,「本当に水の氷だ。もう議論の余地は無い」と自信を見せた。生命に不可欠な水が確認されれば,さらに有機物の検出など生命探しへの期待が拡がる。
←掘削直後の15日(写真左)には左下の日陰部分にあった数個の白い塊が,19日に届いた写真(右)では消えている。』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (f) |
『隕石 水の分子10倍
−NASA検出 火星に水 裏付け− 』 (読売新聞 2013,1,5(夕刊)より引用)
--------------------------------------------------------------------------- |
|
|
 |
|
『米航空宇宙局(NASA)は火星から飛来したとみられる2億年前の隕石(写真,NASA提供)から,従来の10倍もの水の分子を検出したと発表した。
この隕石は,重さ320gで,2011年にサハラ砂漠で見つかった。「ブラックビューティの名称がつけられている。米ニューメキシコ大などの研究チームがかけらを分析したところ,これまでの探査で分かっている火星表面の岩石と組成が非常に良く似ていることが判明。さらに加熱して出てきた気体を調べると従来よりも大量の水の分子が見つかった。
研究チームは「約20臆年前の火星表面の環境などを知る大きな手がかりになるだろう」としている。』 |
|
|
|
|
| (2) |
未知の惑星 |
| (a) |
『太陽系に第9惑星
−海王星の外側 神戸大が理論予測−』 (読売新聞 2008,2,28 より引用)
----------------------------------------------------------------- |
|
『太陽系9番目となる未知の惑星が海王星の外側に存在する可能性の高いことを,神戸大のパトリック・S・リカフィカ研究員と向井教授が,詳細な理論計算で世界で初めて突き止めた。観測体制が整えば,10年以内にも発見されそうだという。4月発行の米天文学専門誌に発表される。』 |
|
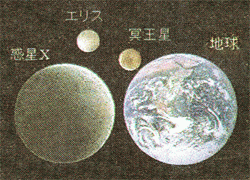 |
「惑星X」の想像図。冥王星の惑星除外のきっかけとなったエリスより,はるかに大きい。
(リカフィカ研究員提供) |
| <2008,6,15 NHKTV「サイエンスゼロ」でも紹介されました> |
|
|
『太陽系の縁では,「太陽系外縁天体」と呼ばれる1,100個以上の小天体が,海王星の外側を回っている。多くは8惑星と同じようなほぼ円形の軌道をとるが,中には大きくくずれている天体もあり,なぜ変則的な軌道を持つのかが大きな謎だった。
リカフィカ研究員らは,太陽系ができ初めて間もない40億年前から現在までの惑星や太陽系外縁天体の軌道の変化を,最も有力な太陽系形成理論に基づきコンピュータで計算。水星から海王星までの8惑星だけでは変則的な外縁天体の軌道を説明できず,新たな「惑星X」を仮想的に加えて計算することで,それが可能になることがわかった。
「惑星X」は,長半径が150億〜260億kmの楕円軌道を回っている。重さは地球の3〜7割で,この領域に多い氷と岩石でできた天体だと仮定すると,直径は地球の約12,700kmに匹敵する10,000〜16,000kmになるという。』
|
|
|
| (b) |
『太陽系外惑星に有機物
−地球から63光年 NASAなど−』 (読売新聞 2008,3,21 より引用)
------------------------------------------------------------------ |
|
『地球から63光年離れた惑星の大気中にメタンの含まれていることが,ハッブル宇宙望遠鏡による観測でわかった。太陽系外の惑星で有機物が見つかったのは初めて。米航空宇宙局(NASA)などの研究チームが20付の英科学誌ネイチャーに発表した。』 |
|
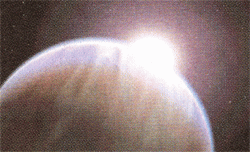 |
有機物が見つかった惑星の想像図
(NASA提供)
|
|
|
『この惑星はこぎつね座にある,木星ほどの大きさの「HD189733b」。昨年5月,恒星の手前を惑星が通り過ぎた際に,その大気を通過してきた光を分析し,メタンに吸収される特定の波長が減っているのを確認した。
この惑星は表面温度が900℃もあり,生物の存在は期待できないが,「有機物の確認は太陽系外での生命探しに役立つ」と考えている。』
|
|
|
|