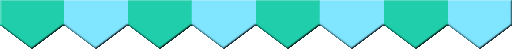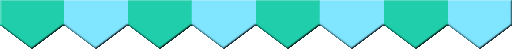|
オコナイ本日(2月15日)
2月15日はあいにくみぞれ混じりの雨になりました。寒い朝でしたが,長年続いた行事はそんなことで休ませてくれません。
午前4時半,長老(オトナ)宅に関係者全員集合,5時30分,まだ夜明け前の暗がりの中を,行列一行が出発しました。
6時,行列が「一の鳥居」をくぐりました。行列の順番は,鋤(すき)持ち(老長)→御幣持ち(脇老長)→「御お桶」<桶持ち>(童女2名)→ゴザ持ち(稚児)→粕酒肴(のぞき)→膳,幟(のぼり),人形→蛇縄→お供,と決まっています。蛇縄と,前日に作られた神饌は,9個に分けられ,担がれています。また,行列は「エトヤ〜,エト,エト」と声を発しています。
6時10分,「二の鳥居」前に設置された左義長横を通過しました。運びこまれた各神饌は,本殿前に一旦整列された後,本殿と末社(8村)に奉納されました。この頃,徐々に日があけてきました。
|
|
<再生ボタンを押してください><音声あり> |
|
|
|
|

女の子は「御お桶」を持参。
(一の鳥居を過ぎた所) |
|
|
|

神饌を一旦本殿前に整列。 |
|

神饌は末社(8村)に奉納し,蛇縄は拝殿に奉納されました。 |
|
|
(↑実際は真っ暗です)
|
「エトヤー,エト,エト」という声を上げながら二の鳥居前を通過。
|
|
|
|
|
|
| 8時,二の鳥居への蛇縄上げです。柱に頭が2回,尻尾が3回巻きつけられ,胴部に4か所,榊が下げられました。 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9時から式典です。拝殿に8村の長老(オトナ),脇長老(ワキオトナ)が参列し,宮司さんのお祓い終了後,今回の世話役である「天王村」の「のぞき」の者の挨拶で直会(なおらい)が始まります。
ここに,末社に奉納されていた,各村割り当ての神饌が運ばれ,酒を酌み交わして終了です。
各村の長老・脇長老は,あらかじめ用意しているトレイなどに神饌を入れ持ち帰り,村の者に分配します。 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
お地盤築(つ)きと「御砂向(おすなむかい)」の神事(3月21日)
老杉神社のオコナイは,2月15日以降もまだまだ続きます。
3月21日は,今年当番になっている天王村の老長(オトナ)宅で,「お地盤(おじばん)」つき(=「お地盤造り」)が行われました。お地盤は「オハケ」ともいい,土をつき固め,芝生を敷いて作った,大きさ2m×1m×高さ90cmの盛り土のことで,神様の“よりしろ(降臨場所)”になる所です。また,3月28日に行われる「お馬神(おうまのかみ)(神の子)」を決めるために必要な場所となります。
このお地盤では,毎年担当の村が新作する際に,前年担当の村が作ったものの土を代々にわたり引継いでいきます。
*)宮司さんによると,オハケは他所でもあるそうですが,こんなに大きな例は無いそうです。 |
|
|
|
老長(オトナ,右)と脇老長(ワキオトナ,左)が,昨年の当番である鉾村の老長宅まで,お地盤の土をもらいに行きます。
もらってきた土を,新作お地盤に引き継ぎます。
 |
|
 |
|
 |
|
| 昨年作られたお地盤 |
|
ここから土を取って→→→ |
|
→→→土を引き継ぎます。 |
|
↓この後,神事を行って無事終了しました。
|
|
|
|
|
|
|
 |
お馬神定め神事(3月31日)
| この日,お地盤にて,「お馬の神さん」を決める重要な神事が行われました。 |
|
| 所定量(1升2合)の米の上に,対象の子供(1〜7歳の対象者:今年の天王村では5名)の名前を書いた小さな紙を散らしておきます。宮司さんがゆっくりと御幣を回し,静電気で紙を1枚だけ付着させ,これを脇老長(ワキオトナ)が扇子を広げて受けます。 |
|
|
|
|
<再生ボタンを押してください><音声あり> |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
| 紙を1枚選定したら,これを別室にて老長(オトナ)が全員の前で読み上げ,お馬神(おうまのかみ)が確定します。 |
|
 |
|
 |
|
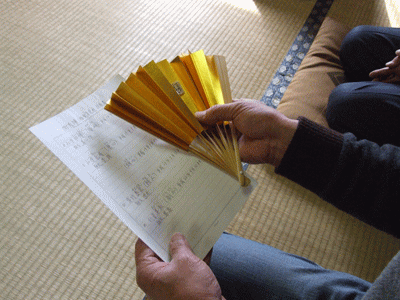 |
|
 |
|
|
|
お馬神が確定すると,さっそくその子どもと親,祖父をよびに行かせ,全員の前で披露されます。
お馬の神としての子どもに赤飯を食べさせた後,全員で直会となります。 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
お地盤ヨシズ,竹矢来,砂盛り(4月17日)
お地盤を守るヨシズと竹矢来の製作,砂盛り作業が行われました。
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 竹矢来は56本と決まっています。最後に注連縄を巻きます。 |
|
|
| お地盤を守る人形は26本(青1,黄1,赤24,白24)。 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
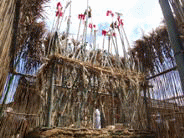 |
|
|
ヨシズを巻きます。 |
|
お地盤ヨシズ完成。 |
|
内部の様子 |
 |
|
 |
|
 |
|
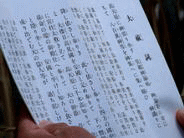 |
| 枡形飯 |
シンコという米粉のねじり御供 |
お地盤ヨシズ完成後の神事 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 砂盛りの場所と個数も決まっています。(左:貴船社前,中:本殿前,右:お旅所前;他にも数カ所あります。) |
|
|
 |
春の例祭とサンヤレ踊り(5月3日)
この日は老杉神社の例祭の日で,天候にも恵まれ,多くの人達で賑わいました。
この日は,オコナイ行事の主担当である天王村(てんのうむら)の人々の社参の後に式典があり,これが終わると,国の無形文化財に指定されている「サンヤレ踊り」の奉納がありました。
その後は,数km離れたお旅所まで天王村の人々を先頭に,神輿4台(大人2台,子供2台),サンヤレ踊り一行と続き,祭りが全て終わったのは夕方6時頃でした。 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 天王村の人達の社参 |
|
女の子も参加(桶持ち)。
(桶には,麻苧(あさお)3結び,ヨシベ3本,カワラケ3枚,白米2合が入っています。) |
|
「のぞき」の宇野氏が担ぐ「ツマミ」入りの桶。↓ |
|
お馬の神さん。
昔はこの地域でも農耕用に馬が飼われていて祭りには実際の馬が登場したようです。また,1の鳥居〜2の鳥居間は200m程あり,競馬をしていたとも。 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
| 社参した天王村の人達 |
|
|
|
(上はアラレ状に切った大根とゆでた大豆,下は酒粕を溶いたもの)
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| サンヤレ踊り |
|
お馬の神さんも祝福対象 |
|
お旅所までの行列 |
|
神輿 |
|
|
〜サンヤレ踊りの起源〜
「サンヤレ」という言葉は「幸あれ」という意味で,サンヤレ踊りは中世に京都で流行した疫病除けの芸能である「風流囃子物」の系譜を引くと考えられています。下笠地区のサンヤレ踊りは,神社の古文書に,応永12年(1405年)に「田楽が奉納されていた」との記述があることから,その頃と考えられています。また,役者達の衣装についても,貞享5年(1688年)の文字のあるものが残っており,江戸時代にはこの形に定まっていたと考えられています。
このようなことから,この踊りは平成5年,国の選択無形文化財に,また衣装も昭和63年に県の有形文化財に指定されました。また,令和4年(2022年)栗東市の「小杖神社の芸能祭礼」とともに『近江湖南のサンヤレ踊り』が全国各地の「風流踊り」の一つとして,ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
なお,4月29日には「ササ踊り」と称して,これらの衣装をつけない形で,同じ踊りが奉納されました。踊りを囲む人達は手に「ササ」を持っていました。このササ踊りは,雨乞いの踊りでもあったようです。
(サンヤレ:参弥礼。サンは「参る」,ヤは「ますますの繁栄」,レは礼儀を尽くす,の意だそうです。)
天王村にまた順番が回ってくるのは,後8年後です。8年後というと,現在の役職(老長他6人衆)のメンバーも変わっているかもしれません。今回も,オコナイの期間中に最長老(本オトナ)の方が亡くなり,メンバーの交代がありました。なにしろ,対象者は皆高齢の方が多いので・・・。
|
|
|
|
|
|
<参考文献> |
|
|
|
1 |
「オコナイ 湖国・祭りのカタチ」:中島・上田・原田著,中島監修,INAX出版発行,2008,6,15
|
|
|
|
2 |
「滋賀の百祭」:大塚虹水著,京都新聞社発行,1990,10,27
|
|
|
|
3 |
「陰陽の世界」:「別冊太陽」西川照子・構成,平凡社発行,2003,2,24
|
|
|
|
4 |
「滋賀県草津市下笠町の宮座と同所老杉神社の神事について」:喜多慶治著,「近畿民族」,1964,34号
|
|